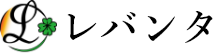ファクタリング利用時の経理はどうなる?仕訳処理完全ガイド
企業の資金調達手段として注目を集めているファクタリング。売掛金を譲渡することで迅速に現金化できる便利なサービスですが、会計処理においては適切な仕訳が必要です。
今回は買取型ファクタリング(償還請求権なし)を中心に、知っておくべきファクタリングの仕訳について、わかりやすく詳しく解説します。
【ファクタリングとは】
まずは、ファクタリングの仕組みや流れを理解しましょう。
<ファクタリングとは?>
ファクタリングとは、企業が保有する売掛金をファクタリング会社に譲渡し、手数料を差し引いた金額を受け取る資金調達方法です。通常の売掛金回収を待つ必要がなく、すぐに現金を手に入れることができるため、キャッシュフロー改善や急な資金需要への対応に効果的です。通常の銀行融資とは異なり、企業の信用力よりも売掛先の信用力が重視されるため、中小企業や経営状況がよくない企業でも比較的利用しやすいという特徴があります。
ファクタリングには大きく分けて「買取型ファクタリング」と「保証型ファクタリング」がありますが、本記事では資金調達に直結する買取型ファクタリング、特に償還請求権なしのものを中心に説明します。
償還請求権なしとは、売掛先が倒産などで支払い不能になった場合でも、利用企業がファクタリング会社に代金を返済する義務がないことを意味しており、より安心して利用できるサービスであるといえます。
買取型ファクタリングの中でも、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの2種類があり、手数料や利用の流れが異なります。2社間は利用企業とファクタリング企業、3社間はそれに売掛先企業を加えた契約となり、2社間は手数料が比較的高く設定されていますが、売掛先に知られることなく、早期(最短即日)に現金化ができることから、国内のファクタリングのほとんどはこの2社間で行われています。
<ファクタリングの流れ>
まず、利用企業とファクタリング会社との間でファクタリング契約を締結します。
次に、利用企業は売掛金をファクタリング会社に売却し、ファクタリング会社は売掛金額から手数料を差し引いた金額を企業に支払います。手数料は数%〜20%程度で、ファクタリングの種類(2社間ファクタリング、3社間ファクタリング)やファクタリング企業によって異なります。
最後に、売掛先からファクタリング会社に直接代金が支払われる(3社間)か、利用企業を経由(2社間)してファクタリング会社に支払われます。
この流れを理解することで、どの段階でどのような仕訳が必要になるかが見えてきます。
【ファクタリングの会計処理における基本的な考え方】
ファクタリングの仕訳を理解するためには、まず基本的な考え方を押さえる必要があります。ファクタリングの会計処理では、売掛金の譲渡が「売買取引」なのか「金融取引」なのかを判断することが重要です。この判断基準は、売掛金に関するリスクと経済価値が実質的に移転しているかどうかにあります。
「買取型ファクタリング(償還請求権なし)」のファクタリングの場合、売掛金の回収リスクがファクタリング会社に移転するため、一般的に売買取引として処理されます。一方、償還請求権ありの場合は、回収リスクが残るため金融取引(借入)として処理される場合がありますが、現在国内で取り扱われているファクタリングのほとんどは償還請求権なしです。
買取型ファクタリングでは、売掛金という資産を現金という資産に変換していることになります。この際、ファクタリング手数料は費用として計上されます。重要なポイントは、ファクタリングは借入金ではなく、売掛金の売却取引であるということです。したがって、負債として計上する必要はありません。これは、企業の財務状況の改善にも寄与する重要な特徴です。
【ファクタリングの基本的な仕訳パターン】
この章では、ファクタリングを利用した際の基本的な仕訳パターンについて解説します。
<ファクタリング時の勘定科目>
ファクタリングを利用して資金調達をした際には以下の勘定項目で仕訳をします。
・売掛金
売掛金は、商品やサービスを提供したものの、まだ代金の回収が完了していない債権を表す勘定科目です。 この債権は将来的に現金として回収される予定の資産であり、貸借対照表上では流動資産として計上されます。 ファクタリング取引においては、この売掛金が資金調達の対象となる重要な要素となります。
・未収入金
未収入金は、企業の主たる営業活動以外から生じた債権で、まだ入金が完了していないものを指します。 この科目も流動資産に分類され、貸借対照表の資産の部に記載されます。 ファクタリング契約では売掛債権の譲渡取引となるため、本来の営業収入とは性質が異なります。そのため、ファクタリング契約成立から実際の入金までの期間において、売掛金勘定から未収入金勘定へと振り替える処理が行われます。 実際にファクタリング会社からの支払いが完了した段階で、現金預金勘定として処理されます。
・売上債権売却損
売上債権売却損は、債権の譲渡や売却取引において発生した損失を会計処理する際に使用される勘定科目です。 買取型ファクタリングを実行する際には、ファクタリング会社に支払う手数料や割引料が発生し、これらの費用がこの勘定科目で処理されることになります。
・支払手数料
支払手数料は、各種サービスの利用に伴って発生する手数料を計上する勘定科目です。 保証型ファクタリングサービスにおいて、売掛債権が予定通り回収された場合に、ファクタリング会社に対して支払う保証手数料がこの科目に該当します。
・貸倒損失
貸倒損失は、取引先の経営破綻や支払不能等により、売掛債権の回収が不可能となった場合の損失を処理する勘定科目です。 保証型ファクタリングサービス利用時に、売掛先企業の倒産等により債権回収が困難となった際の損失額が、この勘定科目で処理されます。
・雑収入
雑収入は、企業の本来の事業活動以外から発生する収入のうち、他の特定の勘定科目に該当しないものを処理する勘定科目です。 保証型ファクタリングサービスにおいて、売掛債権の回収が不能となった際にファクタリング会社から支払われる保証金収入が、この科目で処理されることになります。
<基本的な仕訳パターン>
ファクタリングでは、売掛金の譲渡時に以下の仕訳を行います。
・ファクタリングを契約した際
(借方)未収入金 100万円 (貸方)売掛金 100万円
100万円の売掛金で買取ファクタリングを契約した場合は、上記の形で仕訳します。
・売掛金を売却して資金を受け取った際
(借方)現金預金 90万円 (貸方)未収入金 100万円
(借方)売上債権売却損 10万円
売掛金100万円をファクタリング会社に売却し、手数料10%(10万円)を差し引いた90万円を受け取った場合は上記のようになります。
<ファクタリングの種類別仕訳詳細>
2社間ファクタリング、3社間ファクタリングの違いについて紹介します。
・売掛先からの入金時の仕訳(2社間ファクタリングの場合)
2社間ファクタリングでは、売掛先からの入金を一旦利用企業が受け取り、その後ファクタリング会社に送金します。
*売掛先から100万円の入金があった場合
(借方)現金預金 100万円 (貸方)預り金 100万円
*ファクタリング会社に100万円を送金した場合
(借方)預り金 100万円 (貸方)現金預金 100万円
・売掛先からの入金時の仕訳(3社間ファクタリングの場合)
3社間ファクタリングでは、売掛先が直接ファクタリング会社に支払うため、利用企業の帳簿上では特別な仕訳は不要です。売掛金はすでにファクタリング実行時に消去されているためです。
<消費税の取り扱い>
ファクタリングにおける消費税の取り扱いは複雑です。売掛金の譲渡自体は非課税取引ですが、ファクタリング手数料については課税対象となる場合があります。
償還請求権なしの場合、手数料部分については消費税が課税されることが一般的です。ただし、手数料の性質や契約内容により非課税となるケースもあり、具体的な判断には税務専門家との相談が重要です。
・手数料に消費税が課税された場合
(借方)現金預金 90万円 (貸方)売掛金 10万円
(借方)売上債権売却損 90,909円
※小数点以下切り捨てor四捨五入
(借方)仮払消費税 9,091円
【ファクタリングの会計処理で注意すべきポイント】
ファクタリングの会計処理では、まず契約内容の詳細確認が最も重要です。償還請求権の有無によって会計処理が根本的に変わるため、契約書の精査は必須となります。
次に売掛金の消込処理を適切に行う必要があります。2社間ファクタリングの場合、ファクタリング後も売掛先からの入金は継続するため、システム上で譲渡済み売掛金を明確に管理し、入金時にはファクタリング会社への送金処理を確実に実行することが求められます。
内部統制の整備も欠かせません。売掛金の二重譲渡防止、適切な承認プロセス、ファクタリング会社との契約管理について、堅牢な統制システムを構築する必要があります。
また、税務上の取り扱いについては会計処理と異なる場合があるため、特に消費税の適用について税務専門家との相談が推奨されます。
監査対応では、売掛金譲渡の法的有効性、償還請求権の範囲、手数料の合理性について文書化し、外部監査人に明確に説明できる体制を整備することが重要です。これらのポイントを押さえることで、適切なファクタリング会計処理が実現できます。
【まとめ】
ファクタリングの仕訳では、償還請求権の有無やファクタリングの種類に応じた会計処理を理解し、契約内容に基づく正しい判断が求められます。消費税の扱いや継続利用時の内部統制も重要です。業種や国際取引、電子記録債権などの特殊なケースでは専門知識が必要となるため、経理担当者は契約内容を正確に把握し、会計基準に沿った処理と税務の専門家との連携が不可欠といえます。
正確な処理が企業の財務状況の透明性につながりますので、監査や税務調査への備えとして資料の保管と内部統制の整備も行いましょう。